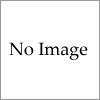
この映画のテーマは死の棘ゆえの魂の苦闘、プラスとマイナスの力の拮抗である。原作に伴う漠然とした陰鬱は、醜の深淵を象徴している。妻ミホの執拗な詰問は、絶望への序曲ではなく、迷いの世界から魂の深みへと潜行するためのセラピーである。
始まりは不倫というありきたりの事件だった。苦悩が主人公トシオから妻ミホ、そして子供たちをも巻き込み、家庭をむしばんでいく。不倫を契機に、静かに眠っていた死の棘が呼び覚まされ、しっと・不信・弁解・欺き・不安をまき散らす。これが私たちの日常性ではないか。やがて、愛人を交えた三者の苦闘へと変わる。三者の桔抗において、死の棘が底知れぬ力を発揮する。特攻隊の生き残り、すでに死をかけてしまったトシオの屍は、錨つな解かれ、欲望の大海を漂うかじ取り不在の小舟である。
圧巻は、精神病院からミホがいなくなるシーンである。真夜中の精神病院の裏庭。濁り水をたたえた水槽の底を竹ざおで突きながら、死体を探すトシオ。涙さえ流さずに。その姿には、私たちの魂の邪悪なものすべてが表現されている。だが、死体は見つからない。トシオは不安を覚え、病棟へ駆け戻る。
何とそこには、先回りしたミホが光の中に立っていた。しかし、驚くべきことは、このときのミホの表情である。憎しみや怒りとは無縁の、慈愛に満ちたほほ笑みで迎える。不実の極み、自らの死さえ望んでいた夫に「あなたが私を呼んだから戻ってきたの」という。
そこには暴力性のない、だが、悪をも善へと変容させる驚くべき力の顕現がある。ミホのひたむきな愛によって、自らの魂と徐々に向き合うトシオ。こだわり続けた死の棘が効力を失い、律法という倫理観、正義観、日常性を超えた不思議な愛が現れる。真剣に人を愛する心の回復である。愛は一方通行では成り立たない。対面を避けてきたトシオを愛の応答へと促す。癒しが必要だったのは、トシオの魂だった。こうしてラストシーンへ収斂する。

魚雷艇学生 (新潮文庫)
この繊細かつ微妙な言葉の呼吸にシンクロできる読者は、相当の読み手。
文章を味読できる人、「文学力」のある人だ。
駄文にまみれた生活を送っている人には、残念ながらこの凄みは分からぬだろう。

死の棘 (新潮文庫)
本というものは読んでも読んでもこの世に数多あり読み尽くすことなどとてもできない。また2度3度
読み返すこともあるわけだから人間生きているうちにいったいどのくらいの本に出会えるのだろうか。
しかしその読書という長い旅のうちに何度かは飛び切りの出会いがある。 まさしくそれがこの作品であった。
自分にとってほんとうに偉大な作家・作品との出会いは、今までウィリアム・フォークナーであったり、
ヘンリー・ジェイムズであったけれどこの作品はそれらの体験に勝るとも劣らない衝撃的な出会いであった。
この見事な日本語で書かれた美しい物語は読み終えたあともいつまでもこころの中から消えない。
寧ろ時間が経つほど波紋のようにこころに染み入っていく。
これはほんとうの物語。ほんとうの愛の物語である。

その夏の今は・夢の中での日常 (講談社文芸文庫)
昭和の大作家島尾敏雄は、芥川賞をのぞく日本文学界の各賞をほぼ総なめにしたにもかかわらず、没後二十数年を経て、「死の棘」、「死の棘日記」以外の作品は、一般に読み親しまれているとは言いがたく、とても残念に感じる。戦争を題材にした物語がエンターテインメント化されてしまった今では、「戦争文学」は若い読者を構えさせてしまうのかもしれない。
しかし、誤解をおそれずに言えば、「出孤島記」「出発は遂に訪れず」「その夏の今は」の、あの八月半ばの日々を綴った一連の作品は、戦争文学であるのに、まるで安部公房をロマンティックにしたように読めるし、「夢の中での日常」「島へ」など幻想的な作品群は、日本版カフカとも言えるだろう。
「あらゆる不幸は実らずに枯れてしまい、中間地帯にとり残されたまま老けてしまう」(「鬼剥げ」)、「不毛への意志のようなもの」(「島へ」)という一節に表われているように、島尾氏の視線は常識的な日常、人がそうであると了解している現実とは別次元で、古びることのない神秘性と暗い端麗さをたたえ、今もパワフルに胸に迫ってくる。
巻末の吉本隆明氏の簡明で味わい深い解説がよいガイドになったが、作品の初出一覧のない点は惜しまれる。復員後まもなくなのか、「死の棘」事件後に書かれたものなのかなどがすぐにわかれば、作品への興味や理解もぐんと深まると思うのだが。
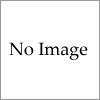
死の棘 [VHS]
小栗監督の作品をゆっくり観てきた。本作だけが未見だったが ようやく今回観る機会を得た。
「死の棘」という言葉は新約聖書コリント人の手紙1の15章から採られている。「死の棘は罪なり、罪の力は律法なり」という一文だ。
本作は夫の浮気という「死の棘」が刺さってしまった家庭の話である。
夫の浮気は別に珍しくもなんともない話だ。陳腐と言って良い。但し 本作が展開する「棘」とは そんなありきたりな話では済まなくなっていく。観ているうちに 狂気に走っているのは妻なのか夫なのかもはっきりしなくなっていくからだ。
しかも 監督は 幾分非現実的なセットを用意して本作を撮っている。観ていると 映画というより演劇のように感じてくる。おまけに季節感が狂ってくる。夏の場面の次には 正月の場面であり まもなくススキが写りだされる。時間の推移ということなのだろうが 観ているこちらとしては 空間的にも時間的にも 混乱させられてくる。観ている場面の季節すら良く分からなくからだ。
狂っているのが 妻や夫だけではなく 観ているこちらまで狂っているような気がしてくるから 不思議だ。
本作の最後に 「救い」は用意されていないと僕は観る。最後の場面に「治癒」が見えるとも思えない。僕らは宙釣りにされたまま.....幾度か首を釣ろうとして失敗していた夫と妻とは違って......本作を観終えることになる。これも得難い体験だ。


![[PS3/JPN] Ar tonelico 3 [Part 197 - Finnel CosmoSphere LVL 7 P.3/6] Ar 197](http://img.youtube.com/vi/UDk9hC2ABcA/3.jpg)



