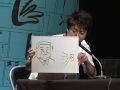1Q84 BOOK 3
雑誌に特集が組まれ、謎解き本が出版されなど、何かと話題の本作だが、
いくら細かく切り刻んだり結びつけたりしてもこの本がなぜこれだけ人気なのかを
説明できているわけではないと私は思う。
これまでのレビューにあるように、女性の体の描写に不快感を抱く読者がおり、
文学の死を叫んだり、社会に対して襟を正せとどなったり、宗教を分かってない
などとこき下ろしたりとさまざまだが、この作品に求めているものが読者によって
異なっているということだろう。
レビューにとらわれずに読んで、楽しんでほしいと私はお薦めする。★5つの
レビューが参考にならなかったと切り捨てられることが多くとも、あえて減点無し
でお薦めしたい。迷っているのなら読んでみたらどうだろうか。
この小説は創作であり、著者が有名だからという理由で比較対象とされる現実の
物事に対する配慮や正確性を求められる必要はない。性的な表現もいつもの村上氏
の味だ。主人公はクリーンである必要はなく、対抗する宗教団体も「悪の組織」で
なければならない理由はない。読む側がそこに個人的な規範を持ち込むから、その
ように不ぞろいな反応が起こるのだ。
あわせて千数百ページの長編を概観することは不可能だが、この物語を通して
作者が語りたかったことのひとつはこうだと想像する。現実社会が実は曖昧で不安定
であり、人々は揺るがない(ように見える)枠に自ら入り込んで生きたがり、その中
で正しいと思われた価値観が、枠の外では反社会的であったり、違法であったりする。
それを描くことで、人々は社会の成り立ちの不確かさや目に見える物事の裏に隠された
「深み」に思いをはせることができる。文学的であることは、公平公正で正義を身に
まとい、理想を標榜することとは無関係だ。まして、勧善懲悪的な構図やスリルを
演出することとも違う。
ストーリーに入り込んで楽しめたこと以外に私が面白いと思ったのは、著者本人の
ものと思われる哲学的な認識が登場人物によって語られていることろだ。特にBook1の
第22章にある「時間と空間と可能性の観念」を人間が脳の発達によって獲得したと
いう記述とそれに続く説明については私の考えに近く、納得したところだ。
全体を通してヤナーチェック作曲の「シンフォニエッタ」が登場する。この曲を私は
高校の頃、実際に演奏したことがある。Book1の冒頭にこの曲が登場したとき、その
重厚な響きを頭の中で蘇らせることができたことも、この小説に入り込むことができた
要因のひとつだろうと個人的に思っている。もちろん、この作品に登場するいかなる
曲や文学作品に触れたことがなくても、ストーリーを、とりあえず目の前に広がった
現実として読み進めれば、最後まで飽きることなく読み通してしまうことだろう。
小説は解釈より「ノメリコミ」が大切!読み進めている最中の気持ちが大事だ。
ストーリーを追体験してつかの間の楽しみを得るためにこそ小説は読まれるべきだと
私は思う。

GamicsシリーズVol.1 横山光輝三国志 第五巻「出師の表」
満員電車の中で読んでも問題なし。
1本に10冊分入っているので、ボリューム感もたっぷり。
左手の人差し指1本で読み進められるのは快感。
難点を挙げるとすれば、
大きなコマの場合いちいちスクロールしてイライラするのと、
読めなさそうで読める字もいちいち拡大してテンポ感が悪いことか。
また、日本漫画史上屈指の名作だけに
将来子供が出来たら読ませたいのだが、
その時にDSというプラットフォームが残っているかどうか・・・
という点だけが紙媒体に劣るところであろう。

おひとり京都の愉しみ (光文社新書)
京都を語っている本は沢山出版されていますが、実際どれだけ体験し、実感しているのかが分からない本が多すぎるように感じていました。そのような状況下で、一番信頼のおける筆者が柏井壽さんだと評価しています。
著者の柏井壽さんは、京都市北区で歯科医院を開業されている生粋の京都人です。すでに京都に関する著作を何冊も表わしている方で、柏木圭一郎の名義で旅情あふれるミステリーも数冊だされている力量の持ち主です。京都の旅のコーディネーターとしてマスコミにも関わっておられ、本書も期待に違わない情報量あふれる作品に仕上がっていました。
第1章の「京都ひとり歩き」からして、実際日頃散策されているルートの紹介ですから、描写の細やかさがたまりません。48ページの「あじき路地」は近年の路地ブームで注目を浴びていますが、このような観光ルートから少し離れた散歩もまた乙なものです。著者の知識量は半端ではありません。文章もとても巧みで含蓄も多く、読んでいてワクワクするような快感に包まれています。
第3章の「京都ひとりランチ」は使えます。グルメ本が大流行りですが、実際自分の味覚と好みを優先しないとあてが外れるでしょう。その点、柏井さんの好みというフィルターがあるにせよ、安定したスタンスで取り上げてあるので是非訪れてください。安くて入りやすいお店が紹介してありますから。
第6章の「京都ひとり晩ごはん」の「割烹はらだ」は、筆者の一押しのお店です。カウンターで一人食べるのには勇気が入りそうですが、筆者のコメントを信じて楽しんでください。
巻末に詳細な地図と、掲載店の住所、電話等の情報が記載してあります。休業中の情報もあり親切な編集になっていますので。

東京時代MAP―大江戸編 (Time trip map-現代地図と歴史地図を重ねた新発想の地図-)
それまで持っていたのが文庫本大のものだったので、B5版のこのMAPは見やすいし、江戸時代の表記のままだと判別しにくいものも活字でわかりやすい。が、千住や向島や新宿などを含む郊外は図版化されておらず、もう少し都市範囲が広ければよかった。