
ステップ!ステップ!ステップ! [DVD]
日本やイギリスでは、社交ダンスは特権階級で教わるイメージです。これは、アメリカの貧民街で暮らす子供たちが授業の一環で行われています。その後、学校対抗で開催されるコンテスト。その中で、子供一人一人がチームワークやダンスに対する姿勢、親の態度など、練習を通して変化していく過程が克明に描かれていました。最後は感動しました。世界中の子供達や親にダンスの良さを知ってもらう意味で見て頂きたい作品です。

Train Out of It
アバンギャルドでパンキッシュ。授業サボって土手淵で昼寝していると聞こえてくるようなのどかで自由な工業ノイズ。ノイバウデンよりもソニックユースよりもはるかにカッコいいです。canの影響もみえますが、全くのオリジナルな雰囲気はPIL以上。是非CANやPILやノイバウデンをすきな人は聴いてください。
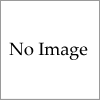
ホットコーヒーを入れて鞄で持ち歩いていましたが、口からコーヒーが洩れてきました。
蓋の締め方が弱いのかと思い強く締めましたが同じです。どうやらパッキンが弱いようです。
クレームを出したところ、翌日に交換してくれました。
交換品は全く洩れません、対策がされていたのでしょうか?
今は機嫌よく使っていますが保温力は弱いです。しかしデザインと質感は非常に良いです。
蓋の締め方が弱いのかと思い強く締めましたが同じです。どうやらパッキンが弱いようです。
クレームを出したところ、翌日に交換してくれました。
交換品は全く洩れません、対策がされていたのでしょうか?
今は機嫌よく使っていますが保温力は弱いです。しかしデザインと質感は非常に良いです。

一回のお客を一生の顧客にする法―顧客満足度No.1ディーラーのノウハウ
ビジネス書は古くなると全然役に立たないものが多いものです。
この本はずい分と前に出ています。 ボクはその時に読んで素晴らしい本だと思いました。
最近新たな仕事を始めるにあたり、また読み直しました。 時間が経ち業種も変わりましたが、やはり素晴らしい本です。
この本はずい分と前に出ています。 ボクはその時に読んで素晴らしい本だと思いました。
最近新たな仕事を始めるにあたり、また読み直しました。 時間が経ち業種も変わりましたが、やはり素晴らしい本です。

職業としてのソフトウェアアーキテクト (Software Architecture Series)
この本の著者にとって、建築とソフトウェアが類似している事を再確認させる事はあまり重要なことではないのかもしれません。
ソフトウェアと建築のアナロジーは、もう何年も前からソフトウェアの業界で言われている事で、最近新装版が出された「人月の神話」では「建築にたとえることはもう有用さを失った」とまで書いているぐらいですから・・・。
ということはさておき、
ソフトウェアの比較として「建築」が取り上げられているのかは、目に不自由がない限り、建築物は誰もが目にする対象であり、ごく一般的で分かりやすいものであるから、あえて著者が選んだのだと考えます。
著者が訴えたかった事は、何かを考えると、
実例まで挙げている、業界が抱えている危機についてではないでしょうか。!
この本を、何かの「答え」が書いてあるものと考えると、きっと読み辛いのではないでしょうか。
「HowTo本ではない」と認識して読まないと途中で挫折してしまうかもしれません。
ソフトウェア業界に身を置く人間が、この本を読み、現状の問題点に気付き、その改善によって、迫っている危機を回避する契機になればという思いを感じます。
ただ本当の意味で、ソフトウェア業界が抱える危うさが改善されるのは、ソフトウェア業界以外の大企業の管理的立場にある人の中に、ソフトウェアの本質を理解した人がもっと増えない限り難しいように感じますが・・・。
ソフトウェアと建築のアナロジーは、もう何年も前からソフトウェアの業界で言われている事で、最近新装版が出された「人月の神話」では「建築にたとえることはもう有用さを失った」とまで書いているぐらいですから・・・。
ということはさておき、
ソフトウェアの比較として「建築」が取り上げられているのかは、目に不自由がない限り、建築物は誰もが目にする対象であり、ごく一般的で分かりやすいものであるから、あえて著者が選んだのだと考えます。
著者が訴えたかった事は、何かを考えると、
実例まで挙げている、業界が抱えている危機についてではないでしょうか。!
この本を、何かの「答え」が書いてあるものと考えると、きっと読み辛いのではないでしょうか。
「HowTo本ではない」と認識して読まないと途中で挫折してしまうかもしれません。
ソフトウェア業界に身を置く人間が、この本を読み、現状の問題点に気付き、その改善によって、迫っている危機を回避する契機になればという思いを感じます。
ただ本当の意味で、ソフトウェア業界が抱える危うさが改善されるのは、ソフトウェア業界以外の大企業の管理的立場にある人の中に、ソフトウェアの本質を理解した人がもっと増えない限り難しいように感じますが・・・。







