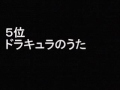古代文明と気候大変動―人類の運命を変えた二万年史 (河出文庫)
長きに亘る自然との闘いと文明の進歩の結果、我々の社会はいまや発展と繁栄の極みを謳歌するに至り、こうした状況は今後も無限に続いていくように思われています。しかしながら、我々の祖先が恐怖と畏敬とを以って接し来たった大自然は、果たして本当に人類の英知の前にひれ伏しているのでしょうか。
本書は、米国の高名な考古学者が、今から約18,000年前にまで遡り、欧州・中東・米大陸等を中心として人類発達の足取りを追いつつ、気候と文明との関係を説き明かそうとする試みです。地球の軌道離心率や太陽活動の変化、海流や氷河の状況、そして火山の活動などにより気候上のパラダイムが変化した際の、人間文明に及ぼされた凄まじいばかりのインパクトを丁寧に解説しています。
そして著者は、文明の進歩により人類は自然に抗う術を獲得してきたものの、居住地移動の可能性の低下やサンクチュアリとしての森や海の消滅に伴う柔軟性の喪失により、今日の先進文明は、「千年に一度」といった規模での気候大変動に対しては却って脆弱性を増していると主張しています。
自然との関係において、人間の営みは、結局のところ、ほんの小さなものに過ぎないのかも知れません。本書を読んで、そんな妙に謙虚な気持ちを味わったことでした。
本書は、米国の高名な考古学者が、今から約18,000年前にまで遡り、欧州・中東・米大陸等を中心として人類発達の足取りを追いつつ、気候と文明との関係を説き明かそうとする試みです。地球の軌道離心率や太陽活動の変化、海流や氷河の状況、そして火山の活動などにより気候上のパラダイムが変化した際の、人間文明に及ぼされた凄まじいばかりのインパクトを丁寧に解説しています。
そして著者は、文明の進歩により人類は自然に抗う術を獲得してきたものの、居住地移動の可能性の低下やサンクチュアリとしての森や海の消滅に伴う柔軟性の喪失により、今日の先進文明は、「千年に一度」といった規模での気候大変動に対しては却って脆弱性を増していると主張しています。
自然との関係において、人間の営みは、結局のところ、ほんの小さなものに過ぎないのかも知れません。本書を読んで、そんな妙に謙虚な気持ちを味わったことでした。

北方領土交渉秘録―失われた五度の機会 (新潮文庫)
エリツィン時代を中心とする、いわゆる「北方領土が最も日本に近付いた時」の記録、回想録である。
ロシア関連のスタイルで五百頁に及ぶ散文の物語にもなっている。
外交の現場を知らない読者にとっては、それでもとにかく何と実のない交渉の連続だったのだろうという気がしてしまうかもしれない。結果としては、著者の云う五度六度のチャンスを逃してしまったと云わねばならないからだ。
しかし、どうであろう。ソビエト時代からすれば、混乱し独裁的にもなった面があるとは言え、開かれて自由にもなった、エピローグで初めて感懐するように「巨大な変化は、明確に好ましいものであった」のではないか。そして、領土返還が最終のゴールに辿り付けなかった理由は、誰か独りの所為と云うのでもなく当事者の「勇気と決断がもう一つ欠けていた」からだという結論に達しする。
逆に言えば、ソビエト崩壊は日露間だけを観た時に、領土返還は既に可能にしているのに、それを実行するという事が日米日中の関係を超えて日露がより密な関係になり得る事を示しているが故に、それは相応の軋轢をも生み控えられざるを得なかった、という穿った見方もできる。著者等が十五年を掛けて懇切に明確なものにしてきた56年の日ソ共同宣言(二島返還、二島不文律)をエリツィンもプーチンもはっきりと受け継いでいるのであるから。よって、何によって領土返還が実現していないか、という事は日露関係にだけ帰着するものではないような気に私はなってしまった。
クリル開発の余波で四島開発の環境が改善し整備されだけで消沈したり狼狽したり憤慨したりすべきものでもない。東方全体シベリア全体を見渡しても、そこが保護整備されるには、結局、日本や中国が協力してという事も今後必ず出て来得るだろう。
「まあ、また良い時代が来ることを祈りましょう」と私も言っておきたい。
なお、この二月に文庫化された丹羽實の『日露外交秘話』も合わせて読んでおきたい。
ロシア関連のスタイルで五百頁に及ぶ散文の物語にもなっている。
外交の現場を知らない読者にとっては、それでもとにかく何と実のない交渉の連続だったのだろうという気がしてしまうかもしれない。結果としては、著者の云う五度六度のチャンスを逃してしまったと云わねばならないからだ。
しかし、どうであろう。ソビエト時代からすれば、混乱し独裁的にもなった面があるとは言え、開かれて自由にもなった、エピローグで初めて感懐するように「巨大な変化は、明確に好ましいものであった」のではないか。そして、領土返還が最終のゴールに辿り付けなかった理由は、誰か独りの所為と云うのでもなく当事者の「勇気と決断がもう一つ欠けていた」からだという結論に達しする。
逆に言えば、ソビエト崩壊は日露間だけを観た時に、領土返還は既に可能にしているのに、それを実行するという事が日米日中の関係を超えて日露がより密な関係になり得る事を示しているが故に、それは相応の軋轢をも生み控えられざるを得なかった、という穿った見方もできる。著者等が十五年を掛けて懇切に明確なものにしてきた56年の日ソ共同宣言(二島返還、二島不文律)をエリツィンもプーチンもはっきりと受け継いでいるのであるから。よって、何によって領土返還が実現していないか、という事は日露関係にだけ帰着するものではないような気に私はなってしまった。
クリル開発の余波で四島開発の環境が改善し整備されだけで消沈したり狼狽したり憤慨したりすべきものでもない。東方全体シベリア全体を見渡しても、そこが保護整備されるには、結局、日本や中国が協力してという事も今後必ず出て来得るだろう。
「まあ、また良い時代が来ることを祈りましょう」と私も言っておきたい。
なお、この二月に文庫化された丹羽實の『日露外交秘話』も合わせて読んでおきたい。