
誤解だらけの「危ない話」―食品添加物、遺伝子組み換え、BSEから電磁波まで
まず、マスメディアの中の人自らが書いていることに敬意を表したい。
この人はキャリアも積み、失うものは少ないのかもしれない。
だとしても、今まで自分が関わってきたことを半ば否定するわけだから、それなりのプレッシャーはあると思う。
不安、危険に関わる報道が、マスメディアにとっていかにおいしいかが分かる。
要するに、不安報道は彼らにとってリスクが少なく、一般の支持を得られやすいのだ。
原因の一つには、戦後の経済成長やテレビの発達にあると思う。
決して日本だけが不安を助長する報道をしているわけではないが、特有のやじうま気質もあるのかもしれない。
是正するためには、情報を受け取る側が自分で考えることだ。
そして、メディアに意見を言ったり、不買(不聴)の行動をとっていくしかないと思う。
本書を100%信じる必要もないが、物の見方にはいろいろとあり、報道は部分しか伝えていないということがよく分かる。
こういう類の本がたくさん出てくると、状況も変わっていくのではないかと感じた。
この人はキャリアも積み、失うものは少ないのかもしれない。
だとしても、今まで自分が関わってきたことを半ば否定するわけだから、それなりのプレッシャーはあると思う。
不安、危険に関わる報道が、マスメディアにとっていかにおいしいかが分かる。
要するに、不安報道は彼らにとってリスクが少なく、一般の支持を得られやすいのだ。
原因の一つには、戦後の経済成長やテレビの発達にあると思う。
決して日本だけが不安を助長する報道をしているわけではないが、特有のやじうま気質もあるのかもしれない。
是正するためには、情報を受け取る側が自分で考えることだ。
そして、メディアに意見を言ったり、不買(不聴)の行動をとっていくしかないと思う。
本書を100%信じる必要もないが、物の見方にはいろいろとあり、報道は部分しか伝えていないということがよく分かる。
こういう類の本がたくさん出てくると、状況も変わっていくのではないかと感じた。
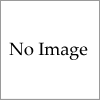
はじめのうちは
漫画で知ってるような絵がアニメーションになってるので見てしまう
でも後半になるにつれて「早いとこ結末を見せてくれないかな」と
思ってしまった
AKIRAは素晴らしい作品だと思うけど、やっぱり漫画の方がいい
漫画で知ってるような絵がアニメーションになってるので見てしまう
でも後半になるにつれて「早いとこ結末を見せてくれないかな」と
思ってしまった
AKIRAは素晴らしい作品だと思うけど、やっぱり漫画の方がいい
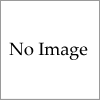
アキラ [VHS]
第三次世界大戦から復興したネオ東京には、健康優良不良少年の金田率いる暴走族が旧市街地に向け暴走していた、その時暴走族のメンバーの鉄雄のバイクは奇妙な少年の力によって爆発、鉄雄は負傷した。そして不思議な力を手に入れた鉄雄は暴走を始める。冒頭のバイクが疾走するシーンはあまりにも有名、天才大友克洋が監督した近未来サイバーパンクストーリー。

食品リスク―BSEとモダニティ (シリーズ生きる思想)
「全頭検査をすれば安全である」というのは全くの勘違いで、「(たとえ全頭検査をしていても)BSE感染牛の肉を食べる可能性がある」ということが理解できてよかった。
時にマニアックと感じるほど「事実」の記述が詳細で読むのが疲れるが、それでも一気に読めてしまうのはプリオンに関係する病気(BSE,ヤコブ病、アルツハイマー?)の研究史が「ドラマ」として抜群におもしろいからだろう。研究者が派閥に分かれ足を引っ張り合う様子は人間くさいし、だがそれほどにプリオン病についてはわかっていないということに驚かされる。
一方で、BSE問題を一番切実な問題としているのが酪農家であることが、明治期の北海道や千葉での酪農史の紹介で思い起こされる。また、普通は触れづらい国会での審議を具体的に(党名、実名入りで!!)とりあげ、政治が悪かった、行政がバカだったという簡単な問題ではないと論ずる。
全編を通して「これからどうしなければならないのか」について著者の熱い思いが伝わってくる。
時にマニアックと感じるほど「事実」の記述が詳細で読むのが疲れるが、それでも一気に読めてしまうのはプリオンに関係する病気(BSE,ヤコブ病、アルツハイマー?)の研究史が「ドラマ」として抜群におもしろいからだろう。研究者が派閥に分かれ足を引っ張り合う様子は人間くさいし、だがそれほどにプリオン病についてはわかっていないということに驚かされる。
一方で、BSE問題を一番切実な問題としているのが酪農家であることが、明治期の北海道や千葉での酪農史の紹介で思い起こされる。また、普通は触れづらい国会での審議を具体的に(党名、実名入りで!!)とりあげ、政治が悪かった、行政がバカだったという簡単な問題ではないと論ずる。
全編を通して「これからどうしなければならないのか」について著者の熱い思いが伝わってくる。







