
キル・ビル Vol.2 [DVD]
教会で横笛が聞こえ“ザ・ブライド”が不安な表情を浮かべる・・・
Vol.2はビルの追撃から始まる、タランティーノ監督のこだわりが全てのシーンからあふれでてそれらを味わい尽くせない自分に苛立ちを感じるほど。
監督の新作が出るまで味わいたい。
人魚ダリル・ハンナが片目の殺し屋、Vol.1では不覚にも気付かなかったが、あの顔・体はアクション向き、ようやく来たか。
タランティーノ監督には勿論これからもこだわりの作品を撮って欲しい。

ヒルズ 挑戦する都市 (朝日新書 200)
ヒルズには少し思い入れがあるのですが、それを振り払っても、
本書の内容は大変に面白く、示唆に富む箇所が多数見られます。
とくに『街メディア』の構想は凄い。
当初からこれを組み込んでいたと考えると、
森ビルは、都市開発だけでなく、
ブランディングやアドバタイジングの世界にも、
進出できるんでは!?と思ってしまいます。
テレビからネットと「メディア」の核は変遷しつつありますが、
ネットの次の「メディア」として、「街」があっても不思議ではないです。
何せ、生身の人間が多数集まると、とんでもないエネルギーが生まれます。
このエネルギーは一種の「麻薬」といえるかも。
ヒルズの歴史を知りたい人はもちろん、
今後の「都市構想」を知りたい人は是非ともお手にとって見てください。
ただし、本書はあくまで「理念」主体です。ご留意くださいませ。
実際の開発計画を知りたい方は「東京計画地図」をどうぞ。
※僕が六本木ヒルズにおもしろさを感じるのは、
アカデミーが備え付けてあるところ。
普通にヒルズで働く人なら、ここの会員になって損はないはず。
何せ、夜中遅くまで開いていて、新刊書籍がたくさん読める…
しかも、めっちゃくつろぎながら。
本好きの方は是非ご利用下さいませ。

森ビル・森トラスト 連戦連勝の経営
港区を歩いていると必ず森ビルのナンバー入りビルを見ることが出来ます。アークヒルズの開発以降は単体のビルではなく大規模複合開発を手がける同社。個々人が都市開発やビル建設の夢を抱いて入社するのがデベロッパーですが、実際にその夢を叶えてくれる会社は少ないものです。森ビルは会社そのものがいつまでも夢を抱き、夢を実現させる唯一のデベロッパーではないでしょうか?本書は森ビルと森トラストの実績、将来展望、財務体質等をあらゆる角度から観察しており大変興味深く読むことが出来ましたが、「森ビル」と「森トラスト」を無理に対比させるのではなく個々の会社をじっくり書き記していただければなお良かったと思います。

Philharmonique;
1stEPもivy;も持ってます。Philharmonique;も、もちろん予約しました。Q;indivi、本当に素晴らしいアーティストです!エレクトロニックなサウンドとアコースティックなサウンドを上手い具合に融合させて、さわやかで優しい近未来的な音楽を次々と生み出します。ヴォーカルの及川リンさんの天使のような歌声も魅力!今作ではメヌエットをベースにした曲や、前作で次回予告のように20秒ほどしか入っていなかった「storia」も収録されるようで、本当に楽しみです!
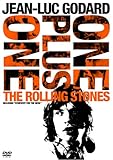
ワン・プラス・ワン/悪魔を憐れむ歌 [DVD]
ストーンズに密着したM・スコセッシの新作がいよいよDVD化されるが、その前にJ・L・ゴダールによるストーンズとのコラボレーション・フィルムが再販。完全版と銘打たれたのは、従来のゴダール版に製作者が商業ベースを考慮して再編集した版が加えられたのが理由だが、監督の意向ならいざ知らず、特にペアリングする意味も感じられないし、ゴダールが激怒するのは当然だが、正直両者には一見しただけでは殆ど違いはない。むしろ、演出指導や"現実"への映画の係わり合いを語るゴダールの姿が見れるメイキングが貴重。
映画は、68年ロンドン、新作アルバム製作中のストーンズのレコーディング風景と黒人過激派ブラックパンサーらによるアジテーションと寸劇をシンクロさせ、楽曲と革命の成り立ちを追った伝説の作品。当時、ゴダールもM・ジャガーもブラックパンサーを熱烈に支持していた。
全編長回しの多用だが、名曲「悪魔を憐れむ歌」誕生までの軌跡が窺えるのが、ストーンズ・ファンには何より魅力だろうが、アンヌ・ヴィアゼムスキーが狂言回し的に何度となく登場し、壁や塀にスローガンを落書きしたり、マオ主義、ボリビア革命、「我が闘争」ら政治的テキストの引用に黒人解放運動の意味と経済的根拠らがインサートされる革命劇はどう映るのだろうか?
ライブでの躍動感とは打って変わってのミックの知的で静かな創作風景と後の自殺を予見する様な淋しげなB・ジョーンズが印象的。
それにしても、40年を経た今日でも色褪せないストーンズの神話的パートと、今日では虚しく忘却の彼方の如き革命劇のパート。68年から遠く離れて、とのフレーズを感じずにはいられないが、若い世代には、これもポップと映るのかも知れない。






